2022.07.29


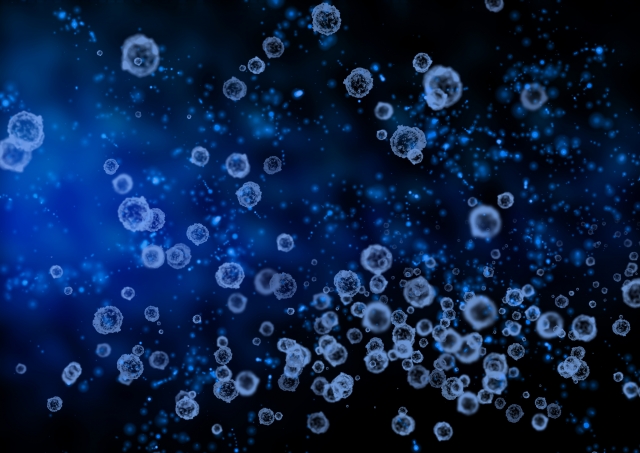
新型コロナウイルスの感染拡大もあり、抗菌・抗ウイルス成分が入った商品に対する関心が高まっているようです。
店頭でも抗菌や抗ウイルスと書かれた商品をよく目にしますが、効果にどのような違いがあるのでしょうか。
菌とウイルス、どちらも目に見えないもので分かりにくいですが、大きく性質が異なります。
抗菌と抗ウイルスの違いや、手軽で効果的な菌・ウイルス対策のアイテムをご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
目次

抗菌や抗ウイルスについて解説する前に、まずは菌とウイルスそれぞれの特徴や違いについて押さえておきましょう。
菌は1つの細胞からなる単細胞生物で、大きさは1~10μm(マイクロメートル)ほど。
μ(マイクロ)は100万分の1を表す単位なので、μmは100万分の1メートルです。
1μmは0.001mmなので、当然のことながら菌は肉眼では確認できません。
菌は皮膚表面など身の回りに多く存在し、生き物のため増殖したり死滅したりします。
菌というと悪いイメージを抱きがちですが、サルモネラ菌や結核菌など有害な菌からビフィズス菌や乳酸菌など人間にとって有益な菌までさまざまです。
ウイルスは菌よりも小さく、細胞を持っていません。
栄養を必要とせず、細胞がないため他の細胞に入り込んで増殖します。
ウイルスの大きさは、数十~数百nm(ナノメートル)ほど。
n(ナノ)は10億分の1を表す単位なのでnmは10億分の1メートル、ウイルスは電子顕微鏡でなければ確認できない大きさです。
よく知られているウイルスには、インフルエンザウイルスやコロナウイルス、ノロウイルスなどがあります。
菌とウイルス、大きな違いはその増殖方法にあります。
菌は生物なので、栄養があれば細胞分裂をして増殖することが可能です。
一方でウイルスは細胞を持たず、生物ではないため自己増殖はできません。
ウイルスは、他の細胞に入り込んで自分のコピーを作らせ、細胞が破裂したときに飛び出して他の細胞に入り込むことで増殖していきます。
このように、菌は生物なので増殖したり死滅したりしますが、ウイルスはそもそも生物ではないため自己増殖ができず死滅することもないという点が大きな違いです。
菌は対策すれば死滅させることができますが、ウイルスは死滅しないため感染力を失わせる、いわゆる「不活化させる」という対策を取ります。
菌とウイルスが違うということは、当然その対策である抗菌や抗ウイルスにも違いがあります。抗菌と抗ウイルスの違いについてみていきましょう。
「一般社団法人抗菌製品技術協議会(以下SIAA)」によると、抗菌は「製品の表面上における細菌の増殖を抑制すること」と定義されています。
似たような言葉で、「滅菌」や「殺菌」がありますが、こちらは細菌などの微生物を一時的に死滅や除去することです。
さまざまな抗菌加工をしてある製品がありますが、「JIS(日本産業規格)」の規定によると「加工されていない製品の表面と比較し、細菌の増殖割合が100分の1以下(抗菌活性値2以上)である場合、その製品に抗菌効果がある」とされています。
SIAAによると抗ウイルスは「製品上の特定ウイルスの数を減少させること」と定義されています。
先ほどご紹介したとおり、菌と違ってウイルスは生物ではないため死滅しません。
そのため、ウイルスを不活化させたり減少させたりすることが大切なのです。
ウイルスを不活化させるには、次亜塩素酸ナトリウムやアルコール(エタノール)の消毒液でウイルスの組織を破壊します。
組織を破壊することで、ウイルスが細胞に入り込んで増殖する力を失い、不活化するのです。
ウイルスは細胞に入り込まないと増殖できないため、例えば何かの製品に付着したとしても、そのままの状態ではウイルスが増えることはありません。
製品の表面に付いたウイルスを減少させる効果があるのが、抗ウイルス加工。
SIAAでは、抗ウイルス加工について「加工されていない製品の表面と比較し、ウイルスの数が100分の1以下(抗ウイルス活性値が2以上であるとき)である場合、その製品に抗ウイルス効果がある」と定義しています。
菌とウイルスは性質が異なり、菌は死滅させることができますがウイルスはその効力を抑えることしかできません。
抗菌や抗ウイルスの加工が施されている製品は、それぞれ対処できる内容が違うため目的によって選ぶ必要があります。
抗菌加工は菌の増殖を抑制させ、抗ウイルス加工はウイルスの数を減少させるという役割です。
菌に対して働きかけたい場合に抗ウイルス加工の製品を使ったり、反対にウイルスに対して働きかけたいのに抗菌加工の製品を使ったりといったことをせず、用途に合わせて使い分けることが重要です。

ここまで菌やウイルス、さらには抗菌や抗ウイルス加工について解説してきました。
しかし、身の回りのすべての製品を抗菌や抗ウイルス加工されたものに買い替えるのは、難しいのではないでしょうか。
そこでおすすめしたい対策として、今ある製品に抗菌・抗ウイルス加工を施すという方法があります。
ご紹介するアイテムは、アサヒペンの「APシールド」。
APシールドは、抗ウイルス抗菌性ワックスの「APシールドTYPE6MⅡ」と抗ウイルス・抗菌コーティング剤「APシールドコーティング」の2種類があります。
手軽に使える「APシールドコーティング」は、ホームセンターマガジン「Pacoma」の2022年1月号「家事ラクグッズ対象2022」でグランプリに選出されました。
ここからは、APシールドの魅力についてご紹介しましょう。
※すべての菌やウイルスに対する効果を保証するものではありません
「APシールドは」、帝京大学の実証実験において新型コロナウイルスに対しての抗ウイルス効果が6か月間持続することが証明されています。
実証実験では、コロナウイルスの成分が約81%減少し、さらに屋外で6か月相当の劣化があった場合でも約60%減少することが実証されました。
「APシールド」は雨や紫外線に強いという特徴があるため、屋外の遊具にも使えます。
また、アルコールのように木製品が変色することがなく、特殊加工されていないフローリングや家具などにも使用可能。
塗布する場所によって使用料は異なりますが、かかる費用は1㎡あたり15円~30円程度で半年間効果が持続します。
少量で広い範囲に塗布可能で、高コスパであることも魅力のひとつです。
「APシールドTYPE6MⅡ」は、スプレータイプのボトルに詰替えて使用するのがおすすめ。
「APシールドコーティング」はスプレータイプの容器で販売されているので、そのまま使用できます。
使い方はとても簡単、シュッと吹き付けてから拭き取るように塗り広げます。
広い面に使用する場合は、ワックススポンジなどを使うときれいな仕上がりに。
「APシールド」は、大腸菌や黄色ブドウ球菌、インフルエンザウイルス(A型)などに効果がある成分を配合しています。
透明なところに塗布しても視界をさえぎることがないため、タブレットやスマートフォン、タッチパネルなどにもおすすめです。
「APシールド」は、人体に必要な微量元素の銅をイオン化した成分を主成分としているので、安全性が高い商品です。
病院や介護施設、学校など、お年寄りや子どもが多く集まる場所の使用にも適しています。
使い方も簡単なので、ドアノブや手すり、エレベーターのボタンなどの抗菌・抗ウイルスにもおすすめです。
菌とウイルスは性質が異なるため、その対策である抗菌・抗ウイルスも目的が異なります。
「APシールドなら」、菌・ウイルスの両方に効果を発揮。
安全性が高い抗菌成分で幅広い用途に使えるので、身の回りの菌・ウイルス対策に使用してみてはいかがでしょうか。